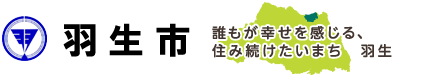公開日 2015年07月03日
更新日 2025年06月17日
保険者
埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます)
住所 さいたま市浦和区北浦和5−6−5 埼玉県浦和合同庁舎4階
電話 048-833-3222
対象者(被保険者)
◆ 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から該当)
◆ 65歳以上で一定の障がいのある方(下記のいずれかに該当する方)で、市に申請して認定を受けた方
a) 身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部に該当する方
※4級の一部
- 「音声機能又は言語障がい」に該当する方
- 「下肢障がい」の1号「両下肢のすべての指を欠くもの」 又は3号「1下肢を下腿の1/2以上で欠くもの」 及び4号の「1下肢の機能の著しい障がい」に該当する方
b) 療育手帳 マルA・A
c) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
d) 障害年金 1・2級
医療機関での窓口負担
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割・2割・3割のいずれか)を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
| 自己負担の割合 | 所得区分 | 住民税課税所得 |
| 1割 | 一般 |
・2割または3割負担の条件に該当しない世帯の被保険者全員 ・被保険者および世帯員のすべてが住民税非課税である世帯の被保険者全員 |
| 2割 | 一定以上所得 |
28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者全員 〇被保険者が1人の世帯の場合 被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上 〇被保険者が2人以上の世帯の場合 被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
| 3割 | 現役並み所得 |
145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 ※住民税課税所得145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。 |
住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると「2割」または「1割」負担になります。
詳しくは患者負担の概要をご覧ください。(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページに移動します。)
| ①被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満 |
| ②被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
| ③被保険者が1人で、同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯 | 被保険者1人の収入が383万円以上で、被保険者と70~74歳の方の収入の合計が520万円未満 |
- 自己負担割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定します。
- 過去にさかのぼって所得更正(修正)があり、それに伴って自己負担割合が上がった場合は、一部負担金の差額を広域連合から請求させていただく場合があります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を引いた金額が210万円以下の場合は、1割負担または2割負担となります。申請は不要です。(平成27年1月1日~)
高額療養費
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(該当される場合は、広域連合から連絡します。)
自己負担限度額
後期高齢者医療制度に移行する月は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来額の2分の1ずつとなります。
| 課税 区分 |
負担 割合 |
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯合算) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 課税 世帯 |
3割 | 現役並み 所得者 |
現役並み所得者Ⅲ (住民税課税所得690万円以上) |
252,600円 |
|
|
現役並み所得者Ⅱ(※2) |
167,400円 (4回目以降は93,000円(※1)) |
||||
|
現役並み所得者Ⅰ(※2) |
80,100円 (4回目以降は44,400円(※1)) |
||||
| 2割 | 一般Ⅱ |
【1】6,000円+(医療費-30,000円(※3))×10% 【2】18,000円 【1】と【2】のいずれか低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円(※1)) |
||
| 1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限144,000円) |
|||
| 非課税 世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
15,000円 | ||||
(※1)12か月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合です。
(※2)低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、受診時に次の確認方法により、同じ月の同じ医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
・マイナ保険証の方…オンライン資格確認
・資格確認書の方…資格確認書の任意記載事項の追記、又はオンライン資格確認
(※3)医療費が30,000円未満の場合は、 30,000円として計算します。
詳しくは高額療養費をご覧ください。(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページに移動します。)
食事療養費標準負担額(入院)
被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、羽生市に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食事代が次のように減額されます。
詳しくは食事療養費標準負担額(入院)をご覧ください。(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページに移動します。)
食事療養標準負担額
| 区分 | 食事療養標準負担額(1食) | ||
|---|---|---|---|
| 【1】 | 現役並み所得者・一般 (【2】及び【3】以外の方) (※1) |
510円 | |
| 【2】 | 低所得者Ⅱ (※2) |
過去1年の入院日数が90日以下 | 240円 |
| 過去1年の入院日数が90日超 | 190円 | ||
| 【3】 | 低所得者Ⅰ (※3) |
110円 | |
(※1)指定難病患者の方は1食あたり300円に据え置かれます。
平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。
(※2)「低所得者Ⅱ」…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
(※3)「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)
生活療養費標準負担額(入院)
被保険者が療養病床(※長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
詳しくは生活療養費標準負担額(入院)をご覧ください。(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページに移動します。)
生活療養標準負担額
入院医療の必要性の高い方以外の患者の場合
| 区 分 | 生活療養標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
| 現役並み所得者・一般 | 510円 (※1) |
370円 | |
| 低所得者Ⅱ | 240円 | ||
| 低所得者Ⅰ (※2) |
老齢福祉年金受給者以外 | 140円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | |
| 指定難病患者 | 食事療養費 標準負担額の表の額 |
0円 | |
(※1)保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
(※3)「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)
入院医療の必要性の高い方の患者の場合
入院医療の必要性が高い方は、食事療養費標準負担額の表の額になります。居住費の負担は、1日につき370円となります。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、「葬祭費」として5万円が広域連合より支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬礼状または葬儀の領収書(葬祭執行者(喪主・施主等)の氏名がわかるもの)
- 葬祭執行者名義の預金通帳
高額介護合算療養費
1年間(算定期間8月1日〜翌年7月1日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額(年額)の合計金額が下記の金額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
申請は7月31日現在で加入している健康保険に対しての申請となります。なお、後期高齢者医療制度に加入で該当している方には申請書を郵送します。
詳しくは高額介護合算療養費をご覧ください。(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページに移動します。)
| 所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 212万円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ | 141万円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 31万円 |
| 低所得Ⅰ | 19万円 | |
※同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は、合算することができません。
※所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
※75歳未満の方で算定期間内に後期高齢者医療制度に加入履歴があっても7月31日現在で他の医療保険制度に加入の方については、7月31日現在加入の医療保険制度への申請となります。その際は、自己負担額証明書が必要となります。
保険料
被保険者全員が保険料を納めます。1年間の保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(所得金額×所得割率)」の合計金額からなり、被保険者一人ひとりに課せられます。
最新の保険料率や、算定の方法の詳細については埼玉県の保険料をご覧ください。(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページへ移動します。
※後期高齢者医療保険料の均等割額と所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ2年ごとに見直しを行うこととなっております。