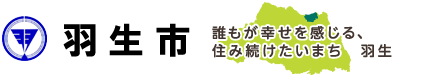公開日 2025年07月15日
更新日 2025年09月01日
概要
令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。その際、減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に金額を算定し、定額減税調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
この度、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、以下の事情により、再算定し、当初調整給付額に不足が生じた方に追加で給付を行います。これを定額減税不足額給付といいます。
給付対象者
令和7年度個人住民税が羽生市で課税(令和7年1月1日に羽生市に住民登録がある方または住民登録外課税されている方)され、以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)との間で差額(不足)が生じた方

給付額
本来給付すべき所要額(万円単位に切上げ)ー 当初調整給付額
手続き方法
対象と思われる方に令和7年8月1日(金)に支給のお知らせもしくは支給確認書を発送いたしました。
《支給のお知らせが届いた方》
原則申請手続きは不要です。不足額は令和7年8月29日(金)に振込みです。
※対象の方は当初調整給付金や低所得世帯向け給付金を受給したことがある方、市税の口座振替の登録がすでにある方です。
※支給のお知らせに記載のある振込み口座を変更したい場合は、令和7年8月15日(金)までに羽生市役所税務課までご連絡ください。
《支給確認書が届いた方》
本市で対象者の口座を把握しておりませんので、原則申請手続きが必要です。
届いた確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類及び通帳の写し等(公金振替口座に振込み希望の場合は通帳の写し等は不要)を同封の上、返信用封筒にて、令和7年10月31日(金)までに申請してください。
※申請期限を過ぎた場合、給付金を受給できませんので、ご注意ください。
※給付金の給付を辞退されたい場合は、辞退の申請を行ってください。
給付対象者となりうる例
例1) 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより 「 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合

令和5年所得に基づく推計所得税額(注1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)(注2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。その場合、調整給付額3万円 と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。
(注1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(注2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
例2) 令和5年中所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)

令和5年中は学生で所得がなかったため、令和6年の推計所得税額(注1)、調整給付額ともに0円であったが、実際には令和6年度から働き始めたため、令和6年所得税額(実績)(注2)が6万円となった。その場合、定額減税可能額(所得税分)3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付される。
(注1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(注2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
例3) 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた場合

令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額が0円(2万円ー2万円)であったが、その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年度住民税所得割が1万円となった。その場合、調整給付額0円と調整給付額(実績)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。
例4) こどもの出生等により扶養親族が増加した場合

令和6年6月時点では、推計所得税額(注1)が8万円、扶養親族が2人であったため定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。そのため調整給付額は1万円(9 万円ー8万円)給付された。その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。そのため、 調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。
(注1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
不足額給付Ⅱ
以下の要件をすべて満たす方
○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外だった)
○税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
○低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
《地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合》
上記条件を満たした上で、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合は、対象となる場合があります。
(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
(イ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
(ウ)令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付額
原則1人4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方は、この限りではありません。
手続き方法
対象と思われる方に令和7年8月22日(金)に支給のお知らせもしくは支給確認書を発送いたしました。
《支給のお知らせが届いた方》
原則申請手続きは不要です。不足額は令和7年9月26日(金)に振込み予定です。
※対象の方は当初調整給付金や低所得世帯向け給付金を受給したことがある方、市税の口座振替の登録がすでにある方です。
※支給のお知らせに記載のある振込み口座を変更したい場合は、令和7年9月12日(金)までに羽生市役所税務課までご連絡ください。
《支給確認書が届いた方》
本市で対象者の口座を把握しておりませんので、原則申請手続きが必要です。
届いた確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類及び通帳の写し等(公金振替口座に振込み希望の場合は通帳の写し等は不要)を同封の上、返信用封筒にて、令和7年10月31日(金)までに申請してください。
※申請期限を過ぎた場合、給付金を受給できませんので、ご注意ください。
※給付金の給付を辞退されたい場合は、辞退の申請を行ってください。
給付対象者となりうる例
例1) 令和6年度住民税所得割課税世帯に属している事業専従者の場合

上記の事業専従者は所得税及び住民税が非課税であり、税法上、専従者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。その場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。
例2) 令和6年度住民税所得割課税世帯に属している「合計所得金額48万円超で令和6年度住民税所得割非課税者」の場合

上記の世帯員は所得税非課税、住民税均等割のみ課税であり、合計所得金額が48万円を超えているため、扶養となることができない。そのため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。その場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。
支給要件を満たすと思われるが、確認書等が届かない方
支給要件を満たすと思われるが、市から書類が届いていない方は申請手続きが必要です。申請する場合は、確認書類(確定申告書や源泉徴収票、当初給付済額がわかる書類等)をご持参の上、税務課窓口にて申請手続きをしてください。
調整給付金をかたった不審な訪問・電話・メールにご注意ください
羽生市や国・県の職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
羽生市や国・県から、「調整給付金の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。また、受給にあたり、手数料の振込みを求めることはありません。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード