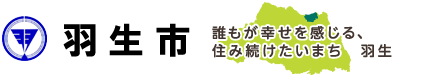公開日 2025年11月07日
更新日 2025年11月07日
令和8年1月1日から、重度心身障がい者医療費助成制度の対象者を拡大します。
新たに対象となる方
以下の両方を満たす方が対象となります。
・65歳に達する誕生日までに精神障害者保健福祉手帳2級を取得し、所持している方
・自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
※上記を満たす方であっても、次の「対象とならない方」のいずれかに該当した場合は対象となりません。
※所得制限があります。
対象とならない方
・生活保護等を受給している方
・小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
・子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度を受給している方
・65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
助成対象となる医療費
1 支給されるもの
自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうち、受給者本人の自己負担分(医療機関窓口での支払い(1割))
2 支給されないもの
・自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。
例:風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
・医療保険が適用されない治療やサービス
例:健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など
申請方法
次のものをご持参のうえ、社会福祉課で申請をしてください。
登録申請をしていただいた後、受給要件の確認を行い、認定となった方には受給者証を交付します。
1.対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証等)
※代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類が必要です。
2.健康保険証又は資格確認書
3.精神障害者保健福祉手帳
4.通帳
5.印鑑(朱肉を使用するもの)
6.個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
※加入している保険や口座等の情報に変更があった場合は、速やかに社会福祉課にて届出をしてください。
有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期限または毎年9月30日のいずれか早いほうが有効期限となります。精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れると、重度心身障がい者医療費助成の有効期限も切れるため、精神障害者保健福祉手帳の更新を忘れずにお願いします。毎年9月中旬に新しい受給者証を発送します。
※自動更新となるため、改めて申請は不要です。制度改正等により申請が必要となる場合は市より通知します。
所得制限について
令和4年10月1日より、重度心身障がい者本人に所得制限基準額を超える所得がある場合は、医療費助成の対象外となります。
・本人所得のみが、対象所得となります。(未成年者も同様)
・1月から9月に受給資格が開始される場合は前々年、10月から12月の場合は前年所得で審査します。
・所得が基準額を超えた場合は、次回更新まで支給停止となり医療費の助成を受けることができません。「医療費支給停止通知」により通知します。
<所得制限の基準額>
扶養親族が0人の場合…3,661,000円(扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算)
・転入等により市で所得が把握できない方は、所得のわかる証明書を提出していただく場合があります。
支給の方法
1 現物給付
県内の医療機関(医科・薬局)を受診する際に、受給者証を提示することにより本人の窓口の支払いがなくなります。
2 償還払い
窓口で支払い後、「重度心身障がい者医療費支給請求書」に医療機関から発行された領収書をのりで貼り付け、社会福祉課へ提出します。診療月の約3か月後に指定の口座へお振込みとなります。
①県外の医療機関等にかかったとき
②現物給付の対応をしていない県内医療機関にかかったとき
③一つの医療機関等での一か月の医療費が21,000円以上になったとき
(羽生市国民健康保険または羽生市後期高齢者医療保険制度以外の健康保険加入者)
④70歳以上の方
(羽生市国民健康保険または羽生市後期高齢者医療保険制度以外の健康保険加入者)
重度心身障がい者医療費支給請求書
請求書に領収書を貼付(注1)し、社会福祉課へ提出してください。なお、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
(注1)領収書を月ごと、医療機関ごと(医科と調剤は分ける)、入院・通院ごとに分けて、
用紙の向きをそろえ、左端をのりで貼り付けます。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(精神通院用)【様式第6号の2】[RTF:144KB]
・重度心身障がい者医療費支給請求書(精神通院用)【様式第6号の2】[DOCX:18.8KB]
※クリーム色の用紙に印刷をしてください。用紙は市社会福祉課で配布しています。
適正受診と医療費削減へご協力のお願い
重度心身障がい者医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。
・急患の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
・普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード