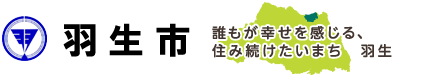公開日 2016年04月01日
更新日 2024年04月09日
定期予防接種
- お子さんが生まれた翌月の下旬に、予防接種の予診票綴り冊子を送付します。
- 転入等で羽生市の予診票をお持ちでない方は、母子手帳をお持ちのうえ、市役所1階の健康づくり推進課へお越しください。
- 転出した場合、羽生市の予診票は使用できません。転出先の市町村へお問合せください。
- 個別接種となりますので、委託医療機関で接種を受けてください。
- 羽生市と契約している埼玉県内の実施医療機関で接種を受けられます。それ以外の医療機関で接種を受ける場合はお問合せください。
- 予防接種の標準的なスケジュールをお子さんに合わせて管理できるシートを作成しました。ぜひご利用ください。
子ども予防接種標準的マイスケジュール[XLSX:116KB]
- ご不明な点は事前にお問合せください。
お知らせ①
【令和6年4月からのワクチンの変更について】
・5種混合ワクチンについて 従来の4種混合ワクチンとヒブにあたる新しいワクチンです。令和6年4月以降に初めて接種する場合は、原則、5種混合ワクチンで接種します。(4種混合ワクチンとヒブの接種歴のあるお子さんは、引き続き同じワクチンで接種を完了します。)
・小児肺炎球菌について 原則PCV15で接種します。PCV15は従来のPCV13と比べて幅広いタイプの肺炎を予防する効果があります。(当面はPCV13で接種する場合があります。)
お知らせ②
【子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種の償還払いについて】
HPV ワクチンの積極的勧奨差し控えで定期接種の機会を逃し、令和4 年3月31 日までに自己負担で接種した対象者に償還払い( 払い戻し)を行います。
対象者:以下のすべてに当てはまる方
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女子で、令和4年4月1日時点で羽生市に住民票がある(その後、羽生市を転出していても対象になります)
- 16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生相当の3月31日)までにHPVワクチンを3回接種していない
- 17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生相当の4月1日)から令和4年3月31日までにHPVワクチン(2価サーバリックスまたは4価ガーダシル)を自費で受けた
- 令和4年4月1日以降、償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種によるHPVワクチンを受けていない
申請期間:令和7年3月31日まで
お知らせ③
【9価のHPVワクチンを公費で接種できるようになりました】
令和5年4月1日から、9価のHPVワクチン(シルガード)を公費で接種できるようになりました。
1.対象者について
定期接種 中学1年生から高校1年生相当の年齢の女子
キャッチアップ接種 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子で、HPVワクチンを3回接種していない方
2.接種回数について
9価ワクチン(シルガード9)で接種を開始する方は、決められた間隔をあけて、合計2回または3回接種します。
1回目または2回目に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることができます。
3.これまでに、2価 または 4価のHPVワクチン(サーバリックスまたはガーダシル)を1回または2回接種した方について
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。この場合にも公費で接種することができます。
その他は次のページをご覧ください
■令和5(2023)年4月より9価の「HPVワクチン」を公費で接種できるようになりました
個別接種
|
ワクチン名 |
標準的接種期間 |
対象者 |
||||||||||
|
実施方法 |
||||||||||||
|
ロタウイルスワクチンは、2種類あります。いずれか一方を最後まで接種してください。 |
||||||||||||
|
ロタウイルス (ロタテック) |
生後2か月~生後32週
|
生後6週~生後32週まで 計3回を経口接種
初回接種は、生後14週6日までに済ませてください。 |
||||||||||
|
ロタウイルス (ロタリックス) |
生後2か月~生後24週
|
生後6週~生後24週まで 計2回を経口接種
初回接種は、生後14週6日までに済ませてください。 |
||||||||||
|
【共通】
※R2.8.1以降に生まれた方が定期接種の対象となります。
|
※R2.10.1以前に接種したものについては、実費になります。 また、その分は定期接種とみなします。残りの回数を接種してください。 |
対象者から除外される方
|
||||||||||
|
小児用肺炎球菌 接種を開始する月齢 (年齢)によって接種回数が1回から4回と異なります。 |
初回 生後2か月~生後7か月に至るまで 追加 生後12か月~生後15か月に至るまで |
生後2か月~5歳に至るまで (生後2か月~5歳になる前日まで) |
||||||||||
| 生後2か月~生後7か月に至るまで |
【初回】(標準的には生後12か月までに)27日以上の間隔で3回接種 ※初回2回目及び3回目の接種は生後24か月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能) ※初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わない(追加接種は実施可能) |
|||||||||||
| 生後7か月~生後12か月に至るまで |
【初回】(標準的には生後12か月までに)27日以上の間隔で2回接種 ※初回2回目の接種は生後24か月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能) 【追加】初回接種終了後60日以上の間隔をあけた後、かつ生後12か月以降に1回接種 |
|||||||||||
| 1歳~2歳に至るまで | 60日以上の間隔で2回接種 | |||||||||||
| 2歳~5歳に至るまで | 1回接種 | |||||||||||
|
BCG |
生後5か月~生後8か月に達するまで |
1歳に至るまで接種可能 (1歳になる前日まで) |
||||||||||
|
1回接種 |
||||||||||||
|
B型肝炎 ※H28.4.1以降に生まれた方が定期接種の対象となります。
※HBs抗原陽性の母親から生まれた児は健康保険の適用となるため、定期接種の対象とはなりません。 |
生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで
1回目は生後2か月、2回目は生後3か月、3回目は生後7~8か月) |
1歳に至るまで接種可能 (1歳になる前日まで) |
||||||||||
|
1回目、2回目:27日以上の間隔をあけて接種 3回目:1回目接種から139日以上の間隔をあけて1回接種
|
||||||||||||
|
R6年度の混合ワクチンの変更点 ※R6年3月中の接種開始→四種混合とヒブで完了します ※R6年4月以降の接種開始→原則五種混合で完了します (ただし、当面は状況により四種とヒブでの接種も可能です。同じワクチンで完了します。) |
||||||||||||
|
五種混合※ ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・ヒブ (R6.4~実施)
※四種・ヒブの接種歴のないお子さん |
1期初回 生後2か月~生後7か月に達するまで
1期追加 1期初回接種終了後6か月~18か月までの間隔をおく |
生後2か月~生後90か月に至るまで (7歳6か月になる前日まで) |
||||||||||
|
1期初回:20日以上(標準的には56日まで)の間隔で3回接種 1期追加 :初回接種終了後6か月以上(標準的には6か月~18か月まで)の間隔で1回接種 |
||||||||||||
|
四種混合※ ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)
※四種の接種歴のあるお子さん |
1期初回 生後2か月~生後12か月に達するまで
1期追加 1期初回接種終了後12か月~18か月までの間隔をおく |
生後2か月~生後90か月に至るまで (7歳6か月になる前日まで) |
||||||||||
|
1期初回:20日以上(標準的には56日まで)の間隔で3回接種
1期追加 :初回接種終了後6か月以上(標準的には12か月~18か月まで)の間隔で1回接種 |
||||||||||||
|
ヒブ ※ヒブの接種歴のあるお子さん 接種を開始する月齢(年齢)によって接種回数が1回から4回と異なります。 |
初回 生後2か月~生後7か月に至るまで 追加 初回接種終了後、7か月から13か月までの間隔をおく |
生後2か月~5歳に至るまで (生後2か月~5歳になる前日まで) |
||||||||||
|
生後2か月~生後7か月に至るまで |
【初回】27日以上(標準的には56日まで)の間隔で3回接種 ※初回2回目及び3回目の接種は生後12か月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能であるが、初回接種終了後、27日以上の間隔をあけて1回行う 【追加】初回接種終了後7か月以上(標準的には13か月まで)の間隔で1回接種 |
|||||||||||
|
生後7か月~生後12か月に至るまで |
【初回】27日以上(標準的には56日まで)の間隔で2回接種 ※初回2回目の接種は生後12か月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能であるが、初回接種終了後、27日以上の間隔をあけて1回行う 【追加】初回接種終了後7か月以上(標準的には13か月まで)の間隔 で1回接種 |
|||||||||||
|
1歳~5歳に至るまで |
1回接種 |
|||||||||||
|
水痘(水ぼうそう)
※既に水痘を発症したことがある方は、公費による接種は対象外です。 |
初回接種 生後12か月~生後15か月に達するまで
追加接種 1回目接種終了後6か月~12か月までの間隔をおく |
生後12か月~生後36か月に至るまで (生後12か月~3歳になる前日まで) |
||||||||||
|
初回接種:(標準的には)生後12月から生後15月に至るまでに1回接種
追加接種:初回接種完了後、3か月以上(標準的には6か月から12か月まで)の間隔をおいて、1回接種 |
||||||||||||
|
MR混合 (麻しん・風しん) |
1期 1歳~2歳に至るまで
|
1期 生後12か月~生後24か月に至るまで (1歳~2歳になる前日まで)
1期:1回接種 |
||||||||||
|
2期 5歳~6歳の年長児 (就学前)
|
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前~当該始期に達する日の前日まで
2期:1回接種 |
|||||||||||
|
日本脳炎
|
1期初回 3歳~4歳に達するまで |
1期初回 生後3歳~生後90か月に至るまで (生後3歳~7歳6か月になる前日まで) 1期初回:6日以上(標準的には28日まで)の間隔で2回接種 |
||||||||||
|
1期追加 4歳~5歳に達するまで
|
1期追加 1期初回終了後6か月以上を経過し、 生後90か月に至るまで
1期追加:1期初回終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)の間隔で1回接種 |
|||||||||||
|
2期 9歳~10歳に達するまで |
2期 9歳~13歳未満 (9歳~13歳になる前日まで) 2期:1回接種 |
|||||||||||
|
◎未接種および不完全接種の特例について 平成17年度~平成21年度にかけての日本脳炎予防接種の見合わせにより、接種を受けられなかった次の①②のお子さんは、実施期間が延長されました。
|
||||||||||||
|
二種混合 (ジフテリア・破傷風) |
11歳~12歳に達するまで (小学6年生) |
11歳~13歳未満 (11歳~13歳になる前日まで) |
||||||||||
|
2期:1回接種
|
||||||||||||
|
子宮頸がん予防(HPV) (ヒトパピローマウイルス感染症) |
13歳となる日の属する年度の初日~当該年度の末日までの間の女子
(令和4年4月より、積極的勧奨が再開されました。)
※平成9年度~平成19年度生まれの方についてはキャッチアップ接種を実施します。 ※ HPV ワクチンの積極的勧奨差し控えで定期接種の機会を逃し、令和4 年3月31 日までに自己負担で接種した対象者に償還払いを行います。 |
(定期接種) 12歳となる日の属する年度の初日~16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学校6年生~高校1年相当の女子) ※特例的に、平成18・19年度生まれの方は通常の定期接種の年齢を超えても令和7年3月末まで接種できます。
ワクチンは3種類あります。一定の間隔を空けて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。
(キャッチアップ接種) 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子(実施期間は令和7年3月31日まで) ■子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種のキャッチアップ接種について
(償還払い) 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女子で条件を満たす方(実施期間は令和7年3月31日まで)
(これまでに2価または、4価のHPVワクチンを1回または2回接種した方へ) ・原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。
|
||||||||||
※※接種の上限年齢について
「~歳に至るまで」は「~歳の誕生日の前日まで」の意です。
予診票の送付時期について(令和6年度)
●日本脳炎 ・・・ 小学校3年生の方に日本脳炎2期の予診票を5~6月頃に郵送します。
●二種混合(ジフテリア・破傷風) ・・・ 小学校6年生の方に5~6月頃に郵送します。
●子宮頸がん予防(HPV)ワクチン(定期接種)・・・ 中学校1年生相当の女子に6月頃に郵送します。
●子宮頸がん予防(HPV)ワクチン(キャッチアップ)・・・ 高校1年生・高校2年生相当の女子に6月頃に郵送します。
定期の予防接種の実施における保護者以外の同伴について
定期の予防接種には、原則、保護者の同伴を必要としますが、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、予診票に加え、以下の委任状を実施医療機関へご提出ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード