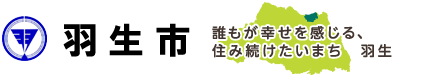公開日 2025年01月07日
更新日 2025年06月26日
埼玉県レッドリスト「野生絶滅」からの脱却!
 令和7年1月7日の埼玉県知事定例記者会見において、埼玉県レッドリスト【植物編】の改訂が公表されました。この中で、 自然の状態ではいなくなり、栽培下でのみ存続している種としてこれまで「野生絶滅」とされていた食虫植物のムジナモが、絶滅の危機には瀕しているものの自然の状態で生育している種として「絶滅危惧Ⅰ類」に変更され、野生復帰することが発表されました。
令和7年1月7日の埼玉県知事定例記者会見において、埼玉県レッドリスト【植物編】の改訂が公表されました。この中で、 自然の状態ではいなくなり、栽培下でのみ存続している種としてこれまで「野生絶滅」とされていた食虫植物のムジナモが、絶滅の危機には瀕しているものの自然の状態で生育している種として「絶滅危惧Ⅰ類」に変更され、野生復帰することが発表されました。
「野生絶滅」から「絶滅危惧」種に変更される野生復帰の事例としては、県内初となります。また、国内で野生復帰した植物としてはイノカシラフラスコモ(東京)、クロタマガヤツリ(千葉)に次いで3例目と全国的にみても大変稀有な事例です。
〇ムジナモとその保護活動についての紹介ページはこちら
〇ムジナモ自生地についての紹介ページはこちら
ムジナモ復活の軌跡
 大字三田ヶ谷にある「宝蔵寺沼ムジナモ自生地」では、大雨による流失や環境変化により、昭和40年代には野生下でのムジナモがみかけられなくなりましたが、羽生市民を中心とした保存会が、それ以前から宝蔵寺沼で採取していたムジナモを自宅で栽培・増殖する活動に取り組み、昭和60年から自生地内での放流を行ってきました。ただ、放流した株は成長するものの、自生地内で越冬して、春に再び浮上する株がみられない期間が長く続きました。
大字三田ヶ谷にある「宝蔵寺沼ムジナモ自生地」では、大雨による流失や環境変化により、昭和40年代には野生下でのムジナモがみかけられなくなりましたが、羽生市民を中心とした保存会が、それ以前から宝蔵寺沼で採取していたムジナモを自宅で栽培・増殖する活動に取り組み、昭和60年から自生地内での放流を行ってきました。ただ、放流した株は成長するものの、自生地内で越冬して、春に再び浮上する株がみられない期間が長く続きました。
平成21年、宝蔵寺沼ムジナモ自生地保存管理計画策定のための緊急調査の際、埼玉大学金子康子教授指導のもと、放流の場所をイヌタヌキモやヒシなどの水生植物が生育している場所に変更したところ、越冬し、再浮上した株が100株ほどみられました。また、当時異常増殖していたウシガエルのオタマジャクシがムジナモなどの水生植物を採食していたことから、この駆除も行うようにしました。その結果、オタマジャクシが少なくなった場所では、多様な水生植物が生育する環境が戻り、その中でムジナモも自然増殖するようになりました。ただ、他の水生植物が多くなりすぎると、ムジナモの生育が阻まれることもわかりました。そのため、水生植物を食べる動物が適度に共存できる環境が望ましいこともわかってきました。保存会などによる放流については、自然繁茂がみられるようになった場所では新たに放流することはせず、生育のみられない場所で放流を行うようにしました。なお、保存会による放流はその役割を終えたと判断されたため、令和4年以降行っていません。
調査の結果、多様な生物がバランスよく成育できる環境がムジナモの生育にもよいことがわかってきたため、以来、その環境を目指して管理を続けたところ、ムジナモの自然増殖が活発になり、平成28年には15万株、令和4年以降には100万株を超える数にまで増えるようになっています。
【5月31日】埼玉大学主催ムジナモ野生復帰記念講演会(終了しました)
【6月15日】宝蔵寺沼ムジナモ自生地特別見学会(終了しました)
【7月16日、23日、30日、8月3日、10日】宝蔵寺沼ムジナモ自生地見学会を開催します。詳細はこちら。